〒182-0006 東京都調布市西つつじヶ丘三丁目26番地7アーバンフラッツMA202
(京王線つつじヶ丘駅北口徒歩2分)
お気軽にお問合せください
(ご予約で時間外でも対応可能)
定休日:土曜・日曜・祝日
(ご予約で対応可能)
民事信託(家族信託)

民事信託(家族信託)は、信託の一種です。
「信託」と聞くと、投資信託や信託銀行等を思い浮かべる方も多いと思いますが、従来から知られている「信託」とは、信託銀行等の信託業者がおこなうもので、これを商事信託と呼ばれるものです。
民事信託とは何かと定義づけるのは、実は簡単ではないのですが、そうした商事信託以外の信託を民事信託と総称すると言ってもいいのではないかと思います。
実は、「家族信託」とは商標登録されている商標なので、その概念は商標登録者が決めるべきものであるかもしれませんが、敢えて言えば、「家族信託」とは、民事信託のうち、家族が中心になって行う信託を指すのではないかと思います。例えば、民事信託の中には、街を再生するための信託のようなものまでありますが、そうしたものは民事信託ではあっても、「家族」信託ではないと思います。
民事信託は、定義づけが難しいことが示すように、幅広い概念を持っていますが、それだけではなく、高い自由度を持った、柔軟性に富む制度になっています。例えば、現在の信託法では、自己信託という委託者が自ら受託者となる信託も認められるに至っています。
民事信託は、そういった高い自由度を持つ制度なので、これまでの相続では対応できなかったような新しい形の相続の形態を可能にします。例えば、跡継ぎ遺贈型の相続は遺言では実現できないとされていますが、受益者連続型の民事信託を利用することで、跡継ぎ遺贈型の遺言と同じ効果を生じさせることができます。
このように新たな形の財産承継や事業承継が可能になるだけでなく、福祉型の信託や不動産管理のための信託など、あらゆる信託が提唱され、実践されています。新しい信託の形態が日々生まれ続けていると言っても過言ではないような状況です
そうした高い自由度を持ち、あらゆるスキームに対応可能な民事信託は、形式的な側面の強い民法上の相続や成年後見に代わるもの、もしくはそれらを補完するものとしてとして今後ますます利用が増えていくものと思われます。
しかし、民事信託の高い自由度は、メリットである半面、熟慮されなかったり、吟味されなかったり、後のことを考えずに安易に作られてしまうリスクがあります。それゆえに、民事信託の効果をあらかじめ見極めたうえで、慎重にスキームを組み立てることが必要とされています。
民事信託(家族信託)の仕組み
信託とは、財産を持っている人(委託者)が誰か(受託者)に財産を信託し、その財産から得られる収益を誰か(受益者)が得るという仕組みです。民事信託の中でも家族信託は、委託者、受託者、受益者といった当事者の全てが家族であるのが一般的であり、そこに大きな特徴があります。
民事信託は、委託者、受託者、受益者の三角関係がその特徴といえます。委託者は、財産を受託者に預けます。そうすると、形式的な所有者は受託者に移ります。通常の所有権は、形式的な所有者が実質的な所有者にもなり、その財産から得られる収益を手にすることになります。一方の信託は、もう一人、受益者という存在が登場します。この受益者がその財産から得られる収益を手にすることになります。
つまり、民事信託を利用すると、従前の所有権を、所有する権利と収益する権利に分け、所有する権利を受託者が担い、収益する権利を受益者が享受することになるのです。言い方を変えると、民事信託を使うと、形式的な所有者と実質的な所有者を別人にすることができるのです。
民事信託は、非常に自由度の高い仕組みなのですが、そのことを示す特徴として、主なもの三つをあげておきます。
まず、委託者と受託者を同一人が担うことができます。これを自己信託と呼びます。委託者自らが、自分自身に対して財産を受託することができるのです。
また、委託者と受益者を同一人にすることもできます。例えば、高齢になり、今後の財産管理に不安を感じたAさんが委託者となり、受託者を息子さんにして、自宅不動産を信託したとします。ここで、Aさん自身を受益者にすることができるのです。受益者となったAさんは、自宅不動産から得られる権利を受益することができる=そのまま自宅に住み続ける権利を得ることができます。自宅不動産から得られる権利とは居住する権利だけでなく、賃貸したり売却益を手にする権利も含まれます。それゆえに、Aさんが元気なうちは自宅に住み続け、認知症になったら、自宅を売却して老人ホームに入るというようなこともできます。
ここで、Aさん自身が自宅を持ち続けているのと違う点があります。
Aさん自身が自宅を持ち続けている場合、認知症になって判断能力が亡くなると自宅を売却できないという可能性が生じてしまいます。一方、信託を利用していれば、受託者である息子の判断で自宅を売却することができ、しかもその売却代金は受益者であるAさんが取得することができるのです。
三つ目の特徴として、受益者を連続して決めることができるという点があります。一次受益者が亡くなったら新たに受益者になる二次受益者や、二次受益者が亡くなったあとに受益者となる三次受益者を決めておくことができます。たとえば、一次受益者をAさん、二次受益者を奥さんのBさん、三次受益者を息子のCさんというように決めておくことができます。
これを利用すると、現在の遺言制度ではできないとされている「後継ぎ遺贈」のようなこともできるようになるなど、従来の相続では実現できなかったような、新たな形の相続を実現させることができるのです。
新しい「相続」としての民事信託(家族信託)
民事信託(家族信託)の仕組みを使うことで、相続や遺言と同様の効果を生み出すことができます。また、従来の相続では実現が難しかったような新たな形の「相続」を実現させることも可能となります。
民事信託で遺言と同様の効果を実現させられる理由
民事信託は、委託者が受託者に財産を託し、受託者が財産の管理や運用を行い、その財産から得られる収益を受益者が享受する仕組みです。
ここで、委託者が受益者になれるということと受益者を連続させることができるのがポイントです。委託者Aを第一次受益者、委託者のお子さんBを第二次受益者とすることができます。
このような場合、委託者=第一次受益者であるAの存命中は、信託財産はAのために使うことができます。Aが亡くなった後は、受益権は第二次受益者であるBに移ります。Aの死亡によって、受益権がAからBに移るのです。
これはあたかも、AがBに相続させる遺言を遺した場合に、Aの死と同時にAからBに遺産の所有権が移るのと同じようなイメージでとらえることができるはずです。
遺言は判断能力さえあれば、いつでも撤回することができます。民事信託の場合、契約ですからいつでも撤回できるわけではないようにも思えますが、契約次第で、撤回することができるように決めておくこともできるし、撤回することができないように定めておくこともできます。
遺言代用信託
後継ぎ遺贈型信託
当相談室の民事信託の特徴
複数の専門家がスキーム作成に関わるので安心です

当相談室は、複数の専門家の協力によって運営されています。
一人の専門家が独断的にことを進めるのではなく、信託条項のリーガルチェックや税金面の検討等を行う形で、複数の専門家が信託条項作成(信託スキーム作成)に関わります。
従って、ご依頼者や専門家の独断による、危険な信託、怪しげな信託、意図しない効果を生んでしまう信託の利用を防止し、安心してご依頼いただけます。
地域密着でいつでも気軽のご相談いただけます

「調布相続相談室」は多摩地区在住の皆様がいつでも気軽にご利用できるような地域密着型のサービスを目指しています。
都心ではなく、地元の専門家にご依頼することで、いつでも気軽に、何度でもご相談に来ていただき、信託契約の条項を詰めていきます。
民事信託や遺言は、ご要望の聞き取りやご依頼者も含めた打合せが非常に重要であり、気軽に何度でも訪れることができる地元の専門家にご依頼することのメリットが非常に高い分野だと思います。
信託契約締結後のアフターフォローも受けられます

当相談室の民事信託は、契約に至ったら終わり、信託の登記が済んだら終わりというわけではありません。
別途報酬をいただくことにはなりますが、受託者となったご家族のフォローを行うことや、信託の見守り、継続的顧問契約等をご利用いただくことで、受託者が一人で放り出されることもなく、事情の変化による信託契約の変更の必要性を見落とすこともなく、継続的に信託のアフターフォローを受けていただくことができます。
民事信託以外の引き出しがあります。
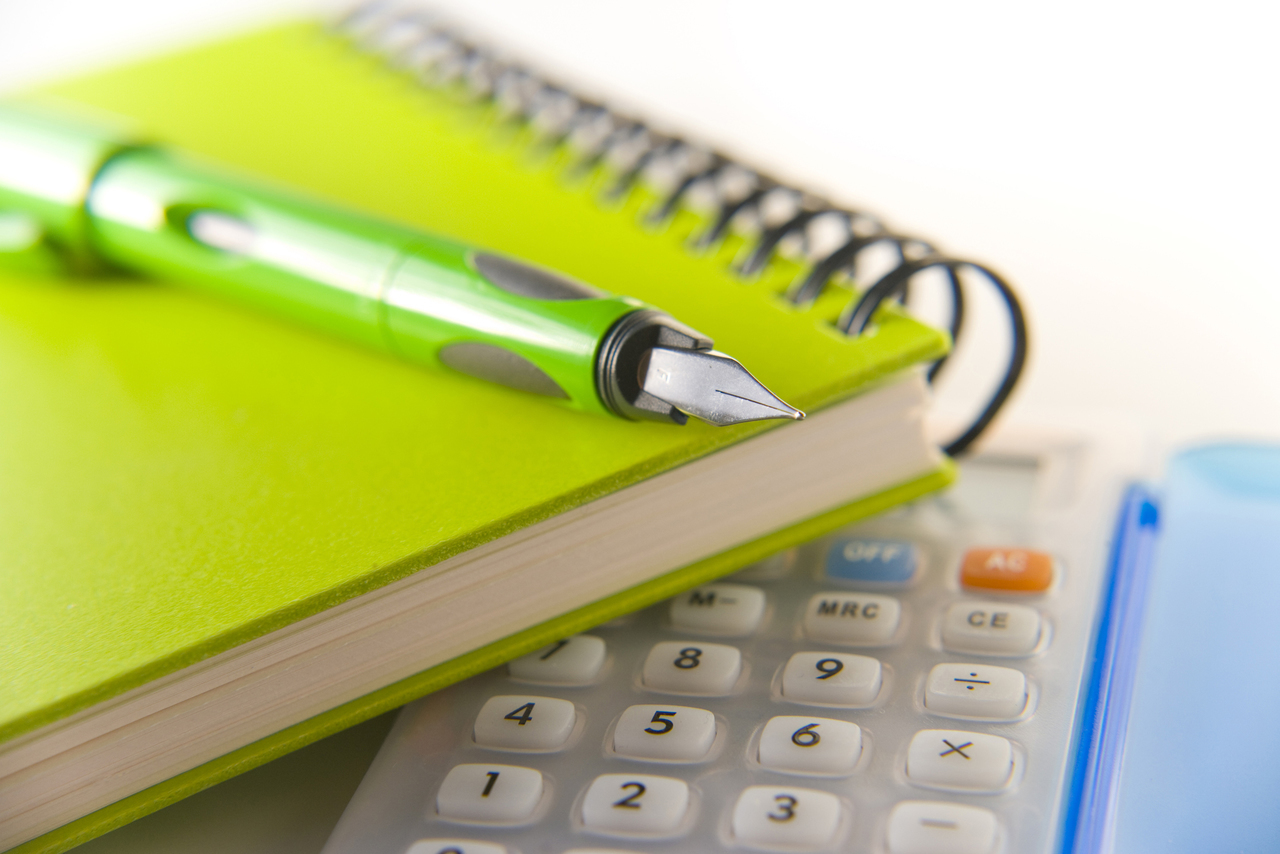
当相談室の運営者や運営協力者は、法定後見や財産管理、相続手続きの経験も有しています。また、法定後見や相続の良いところも問題点も認識しており、民事信託を盲目的に肯定したり、逆に、民事信託をかたくなに否定したりということがありません。
自由な発想で、他の諸制度との比較検討のもと、よりよい制度の利用をご依頼者とご一緒に考えていくのが当相談室のスタンスです。
信託契約締結までの流れ
お問合せから信託契約締結までの流れをご紹介します。
お問合せ

まずは、メールかお電話で、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームからお問い合わせくださるときは、信託を検討している財産の内容や目的等を書いていただけると、その後のお手続がスムーズになります。
代表者による面談
方針の決定
信託契約案の決定
複数の専門家によるチェック
公正証書の作成
信託の登記(不動産がある場合)
信託完了後の見守り(ご希望の場合)
いかがでしょうか。
お気軽にお問合せください
アクセス・受付時間

住所
〒182-0006
東京都調布市西つつじヶ丘三丁目26番地7 アーバンフラッツMA202
アクセス
京王線つつじヶ丘駅徒歩2分
受付時間
8:30~19:00
(ご予約で時間外でも対応可能)
定休日
土曜・日曜・祝日(ご予約で対応可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。
代表者ごあいさつ

地元密着、親切・丁寧な対応を心がけておりますので、まずはお気軽にご相談ください。


